古墳の種類はその形により分類されます。古墳の形の事を「墳形」と言います。古墳の墳形といえば前方後円墳が古墳界のスパースターですが、実は他にも様々な種類の形があります。
また、同じ前方後円墳型でも、年代によって流行のスタイルがあったようで、後円部が大きく前方部が短い短足頭でっかちや、逆に後円部が小さく前方部が細 く長いスタイリッシュな者、くびれがきゅっとしている美人や、寸胴で野暮ったい者、造出しと呼ばれる腕付きの者など、実に様々。
■前方後方墳
前方後円墳の後円部を方形にしたもの。弥生時代終りから古墳時代前半に東日本で多く造られた。京都から千葉県までの伊勢湾沿岸に多くみられる。前方後円墳よりも小型で数も少ない。日本で一番大きい前方後方墳は奈良県天理市の西山古墳(にしやまこふん)で墳長183m、高さ13m。
■円墳
弥生時代から古墳時代に築造。古墳時代に日本全国に分布。小・中規模のものが多い。埼玉県の丸墓山古墳や茨城県の車塚古墳が大きい。日本で一番大きい円墳は奈良県奈良市の富雄丸山古墳(とみおまるやまこふん)で直径109m。 |
| 前方後円墳 |
■前方後円墳
三世紀から七世紀にかけて多く製造された。後円部に死者を葬り、前方部は、元々儀式を行う場所が発達して大きくなったと考えられている。近畿を中心に、南は九州、北は東北まで各地に広がる。日本独特の墳形とされているが韓国にも見られる。三世紀から七世紀にかけて多く製造された。後円部に死者を葬り、前方部は、元々儀式を行う場所が発達して大きくなったと考えられている。近畿を中心に、南は九州、北は東北まで各地に広がる。日本独特の墳形とされているが韓国にも見られる。
 |
| 前方後方墳 |
■前方後方墳
前方後円墳の後円部を方形にしたもの。弥生時代終りから古墳時代前半に東日本で多く造られた。京都から千葉県までの伊勢湾沿岸に多くみられる。前方後円墳よりも小型で数も少ない。日本で一番大きい前方後方墳は奈良県天理市の西山古墳(にしやまこふん)で墳長183m、高さ13m。
 |
| 円墳 |
 |
| 方墳 |
■方墳
近畿・関東に大規模な物が多い。出雲に多くみられる。古墳時代後期に多く採用された。千葉県竜角寺岩屋古墳などが規模が大きい。日本で一番大きな方墳は奈良県橿原市の桝山古墳(ますやまこふん)で一辺:96×90m。
 |
| 八角墳 |
八角形の古墳。畿内の大王のみに許された墳形とされていたが、近年機内以外の豪族墓でも見つかる。奈良県天武・持統天皇陵が有名。また文武天皇陵も八角形であったことが判明した。
 |
| 帆立貝式古墳 |
円墳に造りだしをつけたもの。もしくは前方後円墳のうち、方形の突出部が短いもの。奈良県馬見丘陵公園には大型の帆立貝式前方後円墳が多数みられる。乙女山古墳は墳頂130mあり、国内最大とみられている。
 |
| 双方中円墳 |
■双方中円墳
円丘の両側に方形の突出部を持つ。古墳時代前期に見られる。奈良県天理市にある櫛山古墳など極めて例が少ない。
 |
| 双円墳 |
■双円墳
二基の円墳を連結した形の古墳。大阪府金山古墳が有名。
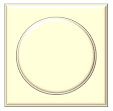 |
| 上円下方墳 |
■上円下方墳
古墳時代終末期に作られ、全国でも5基しか無い。明治・大正・昭和天皇の陵墓はこの墳形である。東京府中にある熊野神社古墳はきれいに復元され資料館も併設されている。
古墳時代終末期に作られ、全国でも5基しか無い。明治・大正・昭和天皇の陵墓はこの墳形である。東京府中にある熊野神社古墳はきれいに復元され資料館も併設されている。
■四隅突出墓(よんすみとっしゅつぼ)
方形周溝墓の外側斜面に石を貼り、隅を突出させたもの。山陰を中心に発達。一つの墓地に群衆して作られている。鳥取県の妻木晩田遺跡などが有名。
古墳時代終末期に作られ、全国でも5基しか無い。明治・大正・昭和天皇の陵墓はこの墳形である。鷹の爪団のダニエルが有名。
方形周溝墓の外側斜面に石を貼り、隅を突出させたもの。山陰を中心に発達。一つの墓地に群衆して作られている。鳥取県の妻木晩田遺跡などが有名。
古墳時代終末期に作られ、全国でも5基しか無い。明治・大正・昭和天皇の陵墓はこの墳形である。鷹の爪団のダニエルが有名。

コメント
コメントを投稿